本と輪 この3冊
君島佐和子さん(「料理通信」編集主幹)に聞いた
料理にまつわる座右の書3冊

2020年10月23日
君島佐和子(「料理通信」編集主幹)
1962年、栃木県生まれ。フリーライターを経て、1995年『料理王国』編集部へ。2002年より編集長を務める。2006年6月、国内外の食の最前線の情報を独自の視点で提示するクリエイティブフードマガジン「料理通信」を創刊。
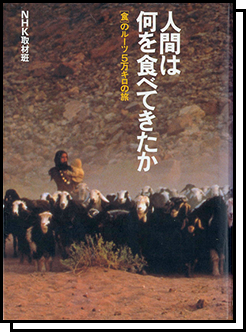
この仕事を重ねてきて、最近とみに興味が食の源流へと向かうのを感じます。それがどうも自分に限った話ではなく、食に携わる人々がこぞってなのです。確立されたメソッドを教わるより、下手でもいいから自分でゼロからやってみる人が増えた。パンのレシピを学ぶのではなく、パンがどうやって作り継がれてきたかを身をもって知ることに意義を見出す若者が増えた。近道せずにあえて遠回りを選ぼうとする、そんな若者たちに読んでほしいのが本書です。
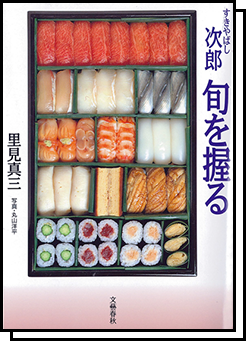
著者の里見真三さんは、文藝春秋社の名物編集者だった人物です。「B級グルメ」という言葉の生みの親でもあります。庶民の味から高嶺の花まで、対象との向き合い方に変わりはなく、その姿勢は「知る」ことと「面白がる」ことの徹底にありました。稀代のすし職人にひっついて、カウンターの向こう側の仕事という仕事を余すところなく写し出した本書は、料理雑誌の編集者としていかにあるべきかを教えてくれました。
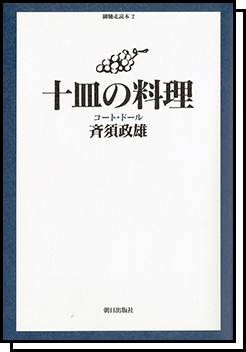
気候風土、民族、歴史が絡み合った上に形作られるのが「食」の様相です。生命と直接的に関わる分、人間の味覚はプリミティブでコンサバティブ。だから、他国の料理を学び、習得するということは、考える以上にハードルが高いと感じます。この本を読む度に胸が詰まって涙が出そうになるのは、あまりにも愚直にそのハードルを越えようとする姿が美しいから。日本のフランス料理界の宝とも言えるこのシェフのありようは、本書で描かれた頃(40年前)も今も変わりません。そこにまた感動している自分がいます。
